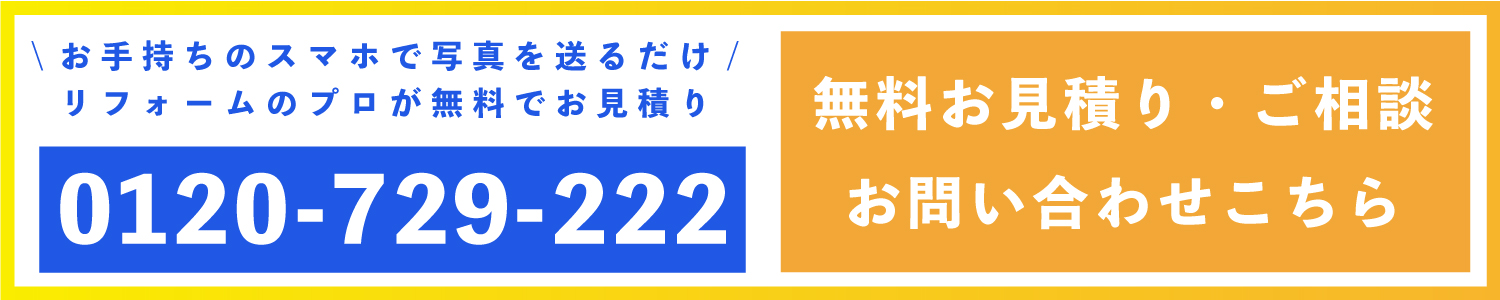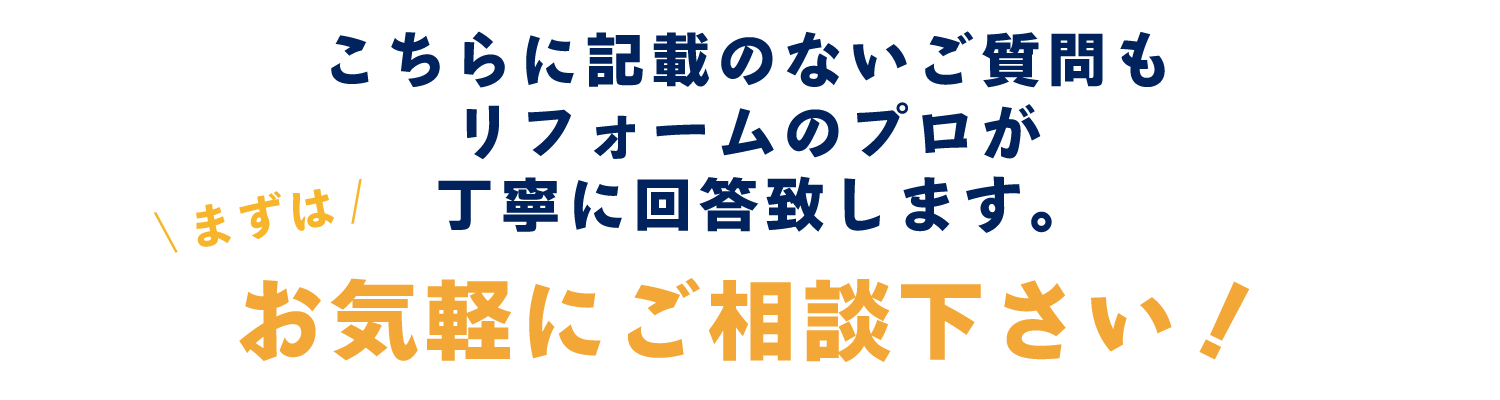
\ タップでお電話いただけます/
営業時間|8:00~19:00
\ フォームで楽々相談/
24時間受付中
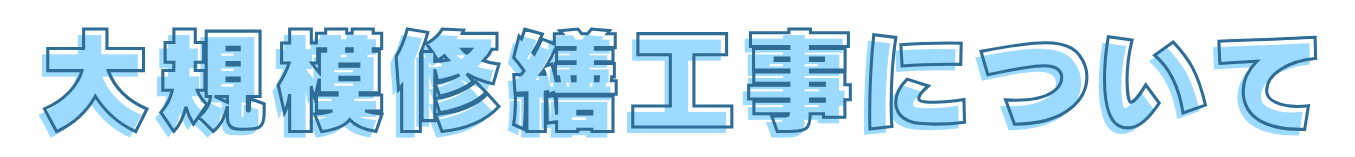
カラーシミュレーションとは、外壁や屋根などの塗装を行う前に、仕上がりの色を事前に確認できるサービスです。実際の写真に色を合成することで、完成後のイメージを視覚的につかむことができます。
通常はお客様のご自宅やマンションなどの外観写真を使い、専用ソフトで希望の色を塗り分けていきます。色見本帳を参考にしながら調整することも可能です。
通常はお客様のご自宅やマンションなどの外観写真を使い、専用ソフトで希望の色を塗り分けていきます。色見本帳を参考にしながら調整することも可能です。
シミュレーションはあくまで完成イメージを確認するためのもので、パソコンやスマホ画面、印刷によって色が変動する場合があります。光の当たり方や塗装後の質感によって実際の仕上がりと若干異なることがあります。実際の仕上がりとは多少差が出ることもあるため、これを目安にしてください。
塗料の色見本やサンプル板を実際に見ていただきますので、カラーシミュレーションと合わせてご確認ください。
もちろんです。2色・3色使いたい、色の切り替え、お好みのお色味など伝えていただければ、ご希望に合ったプランをいくつかご用意させていただきます。
はい、可能です。建物全体のバランスを考慮しながら、外壁・屋根はもちろん、共用部の鉄部や付帯設備(雨どい・サッシなど)も含めたカラーシミュレーションをご提案いたします。複数の配色パターンを確認いただけますので、入居者への印象やブランドイメージに沿ったカラー計画の検討にお役立てください。
はい、対応可能です。ただし、実際の建物外観写真をご提供いただくことで、より現実に近い仕上がりイメージをご確認いただけます。
写真がご用意できない場合でも、弊社保有のモデル画像をもとにしたシミュレーションも可能ですので、イメージ検討の参考としてご活用いただけます。
はい、ございます。賃貸物件や店舗、商業ビルなどでは、入居者や利用者の印象を左右するため、落ち着いた印象や信頼感のあるカラーが選ばれる傾向にあります。
例えば以下のような配色が好まれます
・グレー・ネイビー系:高級感・信頼感・モダンな印象
・ベージュ・アイボリー系:周囲と調和しやすく、清潔感のある印象
・ブラウン系:温かみがあり、安定感を演出
また、企業イメージやブランドカラーに合わせたご提案も可能ですので、お気軽にご相談ください。
色選びにおいては、見た目の印象だけでなく、建物の用途・立地・ターゲット層(入居者・顧客)などを踏まえた設計が重要です。失敗を防ぐためのポイントとして、以下を参考にしてください
・汚れや劣化が目立ちにくい色を選ぶ
・周囲の建物や景観と調和させる
・経年劣化を考慮し、色あせに強い塗料を選定する
・入居者や来訪者に与える印象を意識する(清潔感・安心感・信頼感)
・最終決定前に、実物の塗板での確認を行う
弊社では、物件の価値向上やイメージ戦略も含めたカラー提案を行っております。お気軽にご相談ください。
外壁塗装は、住まいの防水性と美観を保つために、定期的に行う必要があります。1回目の塗装で使った塗料によりますが、1回目の塗り替えから10~15年で2回目の塗り替えをするのが理想的です。
外壁塗装をしないまま放置すると、雨漏りが起こる恐れがあります。塗装によって、家全体は雨風や紫外線から守られています。しかし、経年劣化によって塗装が剥がれてくると、雨水が染み込んできやすくなってしまうのです。雨漏りは、次第に建物内部の柱や土台を腐らせていき、建物全体の劣化を進めていきます。
外壁コーキングの一般的な寿命は、施工後5年~10年とされています。外壁コーキングは、紫外線や気温、乾燥・多湿など天候の影響を受けて少しずつ劣化します。紫外線は、外壁コーキングを劣化させる原因の1つです。
まず住宅にとって雨水の侵入は、建物の構造を劣化させ寿命を縮める大敵です。そこで、外壁の隙間を塞いで防水するのがコーキング(シーリング)の役割です。適切に施工及びメンテナンスをされたコーキング(シーリング)なら、大切なマイホームをしっかり守ってくれます。
コーキングの打ち替えを行うメリットは、前のコーキング材を撤去してから新しいコーキング材を充填するので、耐久性が期待できます。また、目地の隙間をしっかりと埋めることが出来るため、防水性や柔軟性もしっかり確保することが出来ます。
窯業系は20年~40年、木質系は15年~30年、樹脂系は20年~30年が耐用年数の目安です。金属サイディング同様に、この耐用年数の期間サイディングを維持するにはメンテナンスが不可欠です。
窯業系のサイディングは7~10年、木質系だと8~10年、樹脂系は10~20年ほどでメンテナンスが必要とされています。
セメントと繊維を材料に作られていて、耐震性・耐火性に優れているのが特徴。ただしサイディングの上から塗装された塗料が劣化すると、セメント本来の吸水性によし、雨水を吸って劣化しやすくなってしまいます。放っておくと、40年も長持ちしなくなってしまう可能性もあります。
シーリング工事とは、建物の外壁やサッシまわりの目地や接合部に充填されている防水材(シーリング材)を打ち替える、または増し打ちする工事です。雨水の浸入防止や外壁のひび割れ防止、伸縮の吸収といった目的で、建物の耐久性維持において非常に重要なメンテナンスです。
主にALC・パネル構造・タイル張り・サイディング外壁などの建物で必要です。特に、目地の多いビル・集合住宅・商業施設・工場では、定期的な点検と打ち替えが不可欠です。
シーリング材の耐用年数は約10~15年が一般的です。次のような劣化サインがあれば、早めの補修をおすすめします
・ひび割れ・剥がれ
・肉やせ・硬化
・シーリング材の剥離・浮き
・雨漏りや漏水跡
築10年以上経過している物件は、一度専門業者による点検を推奨します。
・打ち替え:既存のシーリング材をすべて撤去し、新しい材料を充填する方法(耐久性が高く、標準的な施工)
・増し打ち:既存のシーリングの上から重ねて充填する方法(応急処置的に用いるケースが多く、耐久性はやや劣ります)
※長期保全を前提とした場合は、打ち替え工事が基本推奨です
基本的に外部作業が中心のため、建物内部に大きな影響はありません。ただし、足場の設置や作業時の騒音、臭気(乾燥前の材料)などは一時的に発生する可能性があります。事前に丁寧な告知や調整を行うことで、トラブル防止につながります。
建物の用途や部位に応じて、**変成シリコン系・ポリウレタン系・高耐久型シーリング材(20年耐用)**などを使い分けます。
紫外線や雨風の影響を受けやすい部位には、高耐候・ノンブリードタイプの材料を推奨しています。
一般的には10~12年ごとが塗り替えの目安とされています。ただし、建物の立地条件(海沿い・新幹線沿い・工業地帯など)や使用塗料、日当たり、劣化状況によって適切な時期は大きく異なります。
当社ではまず外壁のクラック・チョーキング・防水機能の低下などを診断し、「今すぐ必要か」「数年後で良いか」まで含めた最適なタイミングをご提案しています。
住まいにとってとても大切なメンテナンスです。
住まいの外壁は、毎日いろんな環境にさらされていて、風や雨、紫外線や雪などの影響で劣化していきます。
一般的には、外壁塗装は8~15年ごとに行うのが理想とされています。定期的に塗り直すことで、外壁をしっかり保護し、建物の寿命を延ばすことにもつながります。
塗膜の劣化が進むと、ひび割れや剥離が生じたり、カビや藻が生えたりします。それを放置すると、家の劣化が進むことで外壁が腐食したり、室内に漏水が起こったりする可能性もあり、大切な家の価値も下がってしまいます。住まいの外壁に手をかけることで、よりよい状態を長く保つことがあります。
はい、法人様では業務への影響を最小限にすることが最重要と考えています。
足場設置のタイミングや、臭気・騒音の出やすい作業は“業務の妨げにならない時間帯”に調整可能です。
また、従業員様や来客の動線確保、駐車場・搬入口の確保、安全対策も徹底し、通常業務を継続できる工事計画を作成します。
建物の規模・劣化状況・工事内容によって異なりますが、事前に詳細な工程表を作成し、納期を厳守できるよう管理します。
複数棟がある施設では段階施工も可能で、稼働エリアや繁忙期に配慮したスケジュール調整にも対応しています。
法人案件では周辺環境への配慮が非常に重要なため、着工前に近隣挨拶・工程説明を徹底しています。
塗料の飛散防止対策、臭気対策、作業音の管理なども行い、トラックの出入りがある現場では誘導員の配置も可能です。
万が一トラブルが発生した場合も、すぐに対応し、企業様のご負担が出ないよう全て当社で調整します。
はい、カラーシミュレーションにより複数の色パターンを作成し、企業イメージ・周囲との調和・維持管理のしやすさなど総合的に考えたご提案を行っています。
実際の建物写真を基に仕上がりイメージを確認できるため、「完成したら想像と違った」というリスクを減らせます。
多くの法人様は休業できないため、稼働したまま工事を行うケースが一般的です。
動線・荷捌きエリア・休憩所などに支障が出ないようゾーニングを行い、工程を細かく分けて進めます。
作業中も安全確保を最優先し、現場監督が常に状況を把握しながら進行します。
当社では大手塗料メーカーの製品を使用し、塗料ごとの特性・耐候性を踏まえた最適な組み合わせをご提案しています。
また、塗膜保証や工事保証もご用意しており、法人様が安心して長期的に維持管理できる体制を整えています。
はい、現地調査・劣化診断・ご提案書・お見積りまでは無料です。
法人様の場合、数年先の修繕計画に役立つよう、現在の劣化状況をまとめた報告書もあわせてご提出します。
防水工事とは、建物の屋上や屋根・ベランダ・バルコニーなど雨にさらされる場所を自ら守る処置をする工事のことです。
主にコンクリートでできた建物に施工する工事を指します。コンクリートでできた躯体を雨風から守ることで、建物を健康に長く保たせることを目的としています。
防水工事は建物内に水が入らないように行う工事です。防水工事を行わないと、建物内が浸水し雨漏りや腐食が起こり、腐食した木材などを餌にシロアリの被害が出たりと様々な影響が起こります。
防水工事の工法によりたいよ年数が異なりますが、約10年~15年周期で防水工事を行うのが一般的です。防水機能が失われる前に修繕することが大切です。
・FRP防水 : 約10年~15年
・ウレタン防水 : 約10年~13年
・シート防水 : 約12年~15年
・アスファルト防水 : 約12年~20年
建物の耐久性を高め、資産価値を守るために定期的な屋上防水工事は不可欠です。メンテナンスを怠って長年放置し、雨漏りが発生すると、修繕が大ごとになるだけではなく、入居者のパソコンや高級ブランド品などに被害が及び、高額な損害賠償を負う事態にもなりかねません。
雨漏りの原因は主に施工に使われる、防水層・コーキング・笠木・パラペット・排水溝・トップコート・コンクリートなどの劣化が原因です。亀裂や穴あき部分から雨水が屋内に浸透するので、雨漏りの被害につながります。このような劣化に対応するには一般家庭に使われる素材の耐用年数から、10年程度でのメンテナンスが必要です。
雨漏りや床材の劣化を防ぐ為に大切な「ベランダ防水」
そもそも防水の目的は、ベランダの床部分に雨が浸透するのを防ぐ為に行われます。雨が浸透すると、下の階への雨漏りにつながったり、床材そのものが脆くなることでひび割れにつながったりします。
防水層の耐用年数は約10年~15年です。総水槽の素材や建物の立地などで、劣化具合には多少の差が生じます。
ベランダ防水を長持ちさせるためには、5年に1回程度トップコートを塗ることが効果的です。トップコートとは防水層の一番上に施工されるもので、紫外線や摩擦による劣化から防水層を保護するものです。防水層の施工ではなく、表面だけの塗装となります。
バルコニーとベランダの違いは屋根の有無にあります。屋根がなければバルコニー、屋根があればベランダです。どちらも2階以上に設置されることが多いです。
大きい工事だと葺き替え工事・重ね葺き工事(カバー工法)・塗装工事の3つになります。葺き替え工事は今ある屋根材を全て取り新しい屋根をつける工事。重ね葺き工事は今ある屋根材の上に新しい屋根材を張る工事、こちらは撤去作業がない分お安くなります。
塗装工事は今ある屋根材に塗装して今の屋根耐久を高める工事になります。あとは瓦積み直し工事や棟交換工事等の部分工事になります。
屋根工事初日に防水シートまで敷いてあれば問題ありません。屋根を撤去して防水シートを張る日は転機と相談いたします。朝から雨の予報が出ている日などは次の日に延期したりして対応しています。もしも、途中に降ってきても工事を行う際、職人は常に養生道具等を持っていますので緊急対応もできますのでご安心ください。
葺き替え工事は既存の屋根を全て剥がしてから新しい下地(野地盤)を貼増します。その上に防水シートを敷き新しい屋根材を張る方法になります。
重ね葺き工事(カバー工法)は既存屋根の上の棟板金と貫(木下地)を取り屋根をフラットな状態にして既存屋根の上に防水シートを敷き新しい屋根材を貼る工事になります。重ね葺き(カバー工法)は屋根材の撤去がない分お値段的にお安くなります。
屋根だけで完璧な耐震出来るかというと答えはNOですが屋根材を軽量化することで地震対策につながるのは実験でも実証されています。
近年では屋根材自体の性能向上が著しく、製品によっては25年もの保証が付いているものもあります。そのため、20~30年は「何もしなくても大丈夫」と思われがちです。
しかし実際には、例えばストレート屋根などは15年程度で目に見えて劣化が進みますし、屋根材の下に敷いてある防水シートやさらにその下の屋根下地などはそこまで耐久力がありません。
さらに言えば、立地が変われば日照時間も年間雨量も変わるので、高耐久の屋根材を選んだからと言って一概に大丈夫とは言えません。
10年に1度はプロによる屋根診断をお勧めします。
雨漏り箇所の特定など、不具合が起こっている箇所の特定はプロでも経験と知識を要します。
また屋根材が変われば対応策も違ってきますし、何より高所作業なので危険が伴います。10年に1度はプロによる屋根診断を行ってもらい、不具合が見つかれば被害が小さい内に早めに対処する。それが結果的に屋根のメンテナンスにかけるトータルコストを抑え、屋根を長持ちすることに繋がります。

仮設足場を設置せずに外壁工事を行う技術です。国際的な安全規格に基づいて、産業用ロープを使用して高所作業を行います。ブランコ工法とは異なります。
・足場の組み立てが不要:足場を設置しないため、景観を損なわずに施工できます。
・作業場所を選ばない:約40㎝の隙間があれば作業できます。隣家との距離が近い場所でも工事が可能です。
・コスト削減:仮設足場や高所作業車の手配が不要なため、大幅なコスト削減が可能です。
・時間短縮:足場の設置・解体がないため、工期の短縮ができます。
不要です。
景観を邪魔することなく施工でき、防犯面でも安心・安全で、なおかつ工期も短縮できます。
また、隣との境界が狭く足場が組めないような場所や、部分的な修繕もで施工可能です。
40㎝ほどの隙間があれば作業できます。
隣家との距離が近く足場を組むのが困難な場所でも工事可能です。
外壁調査、雨漏り調査・雨漏り対応工事、漏水調査・漏水対応工事、シーリング打ち換え工事、塗装工事、タイル・コンクリート補修工事、雨樋修理工事、防鳥ネット取付工事などがあります。
他にも様々な施工に対応できますので、無理だとあきらめていた工事も、一度ご相談下さい。
・建物の隙間が狭すぎて、足場を組むことが出来ない。隣の建物の敷地を足場用に借りられない、など足場がかけられない環境
・タイル剝落や雨漏りなどで緊急的に部分的な点検・補修が必要だが、足場を組む時間やコストをかけられない。など低コストで部分補修や点検検査が必要
・分割施工による定期メンテナンスで建物を常にいい状態に保ちたいなどのケースに特に強みを発揮できます。
現在のところ、限界はありません。
外壁打診調査とは、その名の通り建物の外壁を、主にハンマーや金属棒などの道具を使って直接叩き音の違いから内部の劣化や剝落のリスクを判断する調査法です。
この方法は「打音調査」とも呼ばれ外壁やモルタルが建物にしっかりと接着されているかどうかを確認すために行われます。
以下の2つの条件の双方に当てはまる建物物が対象です。
①施工や外壁改修から10年以上経過している。
②過去3年以内に打診調査を実施していない。
上記に当てはまっていなくても、手の届く範囲での打診調査や双眼鏡等を使った目視調査で異常が見つかった場合は、打診調査する必要があります。建築基準法により「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な調査」が求められているためです。
ただし、3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合や、歩行者の安全を守るための策を別途講じている場合は、外壁調査の対象とはなりません。
主に以下の6つの方法があります。
● 仮設足場 ● 高所作業車 ● ゴンドラ ● ブランコ ● ロープアクセス ● 赤外線サーモグラフィ
それぞれメリット・デメリットが異なるので、対象建築物に合った方法を選ぶことが大切です。
施工内容 ☜こちらをご確認ください。
建築基準法で外壁打診調査が必要だと判断された場合、下記流れに従って外壁打診調査を行う必要があります。
定期報告対象建築物は、建築基準法と県建築基準法施工細則によって定められているため、各都道府県によって微妙に異なります。一般住宅は対象規模に当てはまらないケースが多いですが、以下のような建築物は定期報告対象となっている場合が多いです。
● 劇場・映画館・演芸場 ●観覧場・公会堂・集会場 ● 病院・診療所(患者の収容施設があるもの) ● 児童福祉施設等 ● ホテル・旅館 ● 下宿・共同住宅・寄宿舎 ● 学校・体育館 ● 博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・水泳場・スポーツの練習場 ●百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・衆浴場・待合・料理店・物品販売業店舗
各都道府県庁のホームページで定期報告の対象規模が公開されているので、所有する建物が当てはまるか確認してみてください。
建築基準法第12条では外壁打診調査を行うことと、定期報告をすることが義務付けられています。
対象物件を所有している責任者が外壁打診調査を行わなかった場合、建物の所有者や管理者に対して罰則が科されることがあります。定期報告義務の違反による罰則として建築基準法に制定されていることを紹介すると
罰金刑 | 定期報告義務違反の罰則
外壁打診調査の対象物件の責任者が定期報告を怠った場合、50万円以下の罰金が課されることがあります。建物の所有者や管理者が定期報告の義務を果たさず、調査報告を行政に提出しなかった場合に適用されることが多いです。罰金額は行政の判断によって異なり、違反の程度や状況に応じて決定されます。罰金は単なる金銭的負担だけでなく、所有者や管理者の責任が問われる形となり、社会的な信用にも影響を与えかねません。
行政からの是正命令 | 定期報告義務違反の罰則
外壁打診調査を行わなかった場合、行政から是正命令が出されることがあります。是正命令とは、法律に違反した場合に行政が違反者に対して速やかに法令順守を促すために発出する命令のこと。具体的には、打診調査を実施してその結果を報告されるよう指示されることが多いです。是正命令を無視した場合は罰金だけでなく、さらなる法的措置が取られる可能性があります。
営業停止や建物使用禁止措置 | 定期報告義務違反の罰則
建物の利用状況や公共性によっては、調査を行わなかった場合に営業停止や使用禁止措置が取られることも。特に多くの人が利用する商業施設や公共施設などで、外壁が危険な状態であると判断された場合に適用されます。使用停止措置が取られると、建物の運用に支障をきたすなど経済的な損失が発生する原因になるので注意が必要です。
外壁打診調査を怠ったことで、外壁が剥がれ落ちて通行人や建物の利用者がケガをした場合は、損害賠償や刑事責任が発生することもあります。外壁打診調査や調査報告を先延ばしにしてもデメリットしかないので、あらかじめ決められたスケジュールで行うようにしてください。
未調査時の損害賠償請求について
外壁の剝落などによって人身事故や物損事故が発生した場合、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。賠償額はケガの程度や被害の規模に応じて変動しますが、大規模な建物での事故の場合は高額な賠償金が発生する傾向が。高額になる場合、所有者や管理者にとって大きな経済的負担となります。
未調査時の刑事責任の追及について
外壁が剝落したことで人命に危害を加えた場合、所有者や管理者には過失致傷罪や過失致死罪が適用される可能性があります。罰金だけでなく刑事責任を問われ、最悪の場合は懲役刑が課されることも。刑事責任が問われることで社会的信用も大きく失われるので、事業の継続が困難になるケースもあります。
建物の資産価値低下 | 外壁打診調査をしない場合のデメリット
外壁打診調査を怠ることで、建物の資産価値が低下する可能性もあります。定期的なメンテナンスが行われていない建物は経年劣化が進行しやすい傾向があり、建物全体の価値が下がるだけでなく、売却や賃貸にも悪影響を及ぼすことも。外壁の状態が悪化したままでは建物の美観も損なわれますので、周囲の環境や景観に悪影響を与える場合もあります。
保険の適用外になる可能性 | 外壁打診調査のデメリット
外壁の定期的な調査やメンテナンスが行われていない状態で事故が発生した場合、保険が適用されない可能性も。多くの損害保険会社は保険金支払いの際に建物の管理状況を確認するため、定期的なメンテナンスが行われているかを確認します。調査を怠っていた場合、「予見可能なリスクを管理しなかった」と見なされてしまい、保険金の支払いが拒否されるケースがあるため注意が必要です。
社会的信用の低下 | 外壁打診調査のデメリット
外壁打診調査を怠ることは、社会的信用の低下にもつながります。商業施設や公共施設を運営する企業や組織の場合、建物化㏍理に関する不備が発覚することで利用者や取引先からの信頼が損なわれる可能性も。建物の安全性が問題視されることで顧客離れが進み、売上の低下にもつながりかねません。安全な建物環境を提供することは、企業のイメージや社会的な評価にも関わるため定期報告を怠らないことが重要です。
建物の漏水にはさまざまな原因がありますが、主なものは以下の通りです
・外壁や屋上防水層の劣化や破損
・シーリングの劣化による目地からの浸水
・配管(給水・排水)の破損や腐食
・サッシまわり・開口部の防水処理不足
・結露や内部の排気・換気不良による水滴発生
原因によって修繕の方法が大きく異なるため、まずは調査・診断が重要です。
漏水箇所の特定には、以下のような調査方法を組み合わせて行います
・目視・打診調査(ひび割れ・シーリング劣化などの外観確認)
・散水調査(疑わしい部位に水をかけて再現確認)
・赤外線サーモグラフィ調査(断熱材・内壁内の水分を感知)
・発煙調査(空調・排気経路の逆流チェック)
・内視鏡調査・配管内カメラ調査(設備系統に異常がある場合)
調査結果をもとに、最も適した工法・範囲を提案します。
放置すると躯体内部の腐食、カビ・腐敗、漏電リスクなどが高まり、被害が拡大する恐れがあります。
特に賃貸物件や商業施設では、入居者・利用者への影響や賠償問題にも発展しかねません。
まずは早急に原因特定と応急処置(仮設防水・シート設置等)を行い、根本修繕へと進むのが望ましいです。
調査結果に応じて、以下のような修繕工事が検討されます
・外壁補修・ひび割れ補修(Uカット・樹脂注入)
・シーリング打ち替え・打ち増し
・屋上防水(ウレタン・シート防水・FRP)
・バルコニー・庇まわりの防水補強
・設備配管の交換・保温材補修・防露処理
建物の構造・用途に合わせた最適な材料・工法をご提案します。
外部からの作業が中心ですが、仮設足場や騒音、資材の搬入・搬出などで、一時的に影響が出る場合があります。
弊社では事前告知文の作成、掲示、スケジュール調整などの対応を行い、入居者・テナント様の安心と協力を得た上で進行いたします。

・外壁のひび割れ:特にモルタル壁の場合は、地震の揺れや経年劣化などによるひび割れが起きていることが多く、5㎜を超える割れ目があると隙間から水が浸入しやすくなります。
・外壁(シーリングの劣化):シーリングは、サイディングの継ぎ目によく使用されます。サイディングそのものには耐久性があっても、シーリングが劣化してひび割れを起こしてしまうと、そこから雨が侵入してしまいます。打ち替えなど定期的なメンテナンスが必要です。
・窓枠・サッシ:外壁との接点があることから隙間が生まれやすい箇所です。原因の一つは窓周りのシーリングの劣化です。
また、窓・サッシのパッキンの不具合でも、雨漏りが発生することがあります。天窓は屋根に取り付けられているため、隙間を伝って雨水が屋内に侵入するリスクは高いといえます。
・屋根(板金):金属製の屋根材の場合、経年劣化でサビがひどくなると穴があいてしまい雨漏りの原因になります。雨漏りするほどのサビが発生していると補修だけでは難しくなるので、酷くなる前に、定期的に塗り替えなどのメンテナンスが必要です。
・屋根(屋根材のひび割れ、ずれ):地震や台風などによって生じた屋根材のひび割れやずれから雨漏りが発生することがあります。
ストレートや瓦材などは強風による飛散物が当たると割れることもありますし、風そのものでずれを起こすこともあります。
・屋根・外壁(釘穴、ビス穴):屋根や外壁は施工の際に、多くの釘やビスが使用されます。経年劣化により腐食が始まると釘やビスがゆるんで隙間ができ、雨漏りが発生します。
・ベランダ(防水層のひび割れ):ベランダの床は防水層で覆われているのが一般的ですが、紫外線や雨風にさらされているため、劣化しやすい箇所です。劣化が進むとひび割れが発生し、防水機能が低下して雨が侵入しやすくなります。ひび割れ箇所から侵入した雨水が建物内部を伝って、思わぬところから雨漏りすることがあります。
・ベランダ(排水ドレンの劣化):排水ドレンの劣化も雨漏りの原因になります。錆びたりごみが詰まり腐食したりすることで、水漏れがしやすくなります。こまめな掃除とメンテナンスが必要です。
・ベランダ(手すりやつなぎ目の隙間、シーリングの劣化):手すりと外壁の接点は、シーリング劣化でひび割れが起こると雨が侵入しやすくなります。屋根よりも張り出した部分は雨風にさらされているため注意が必要です。
・雨どい:雨どいからの水漏れにより、建物内に雨が浸入することがあります。本来なら雨どいの中を流れる雨水が屋根や外壁に漏れてしまうと、雨漏りの原因につながります。
雨漏りは築何年目でも発生する可能性があります。一般的に屋根のリフォームを考える時期の目安は、早いタイミングだと新築から10年目ぐらいです。ただし場合によっては、築10年未満の物件でも雨漏りが発生する可能性もあります。
はい。対応可能となります。
漏水は様々な原因があります。
現状確認後に最適な方法をご提案させていただきます。
はい、もちろんです。気になる症状がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
雨漏りの原因が違う個所にある可能性があるためです。
雨の降り方や風向きにより、雨漏りする箇所が変わるため、雨漏りするときとしないときがあります。
雨漏りを放置すると、シロアリやダニ・カビといった二次災害が発生し、住宅の寿命を縮めるだけでなく、家族の健康にも悪影響があります。雨水は住宅の木部に染み込み、防水シートなどの「建物の内側」から腐らせます。雨漏りを放置して、自然に状態がよくなることは絶対にありません。
屋根からの雨漏りの修理期間は、程度によって1日~2週間です。
瓦のズレが原因のような軽微なものなら1日で直りますが、全体的に補修が必要なら2週間程度は必要になります。
天井からの雨漏りは、3日~1週間の修理期間が必要です。
屋根やベランダ、劣化した外壁など原因を特定し、コーキングで防いだら修理完了です。
散水調査は、専用ホースやノズルで外壁・サッシ・屋根・接合部などに水をかけ、
“実際の雨の状態を再現しながら” 雨漏りの侵入箇所を特定する調査です。
建物の構造に合わせて水の量・角度・時間を調整し、どこから浸水しているのかを丁寧に検証します。
企業施設のように規模が大きく複雑な建物でも、原因箇所の絞り込みに非常に有効です。
ビル・マンション・工場・倉庫・商業施設・オフィスなど、あらゆる法人建物に対応可能です。
特に「雨漏りの原因が不明」「過去に補修したが再発している」「複数の侵入経路が疑われる」場合に最適です。
原則として業務に大きな支障はありません。
室内側では浸水状況を確認するための立ち入りが必要ですが、使用中のエリアは避け、時間帯調整も柔軟に対応します。
大事な設備や商品は事前に養生し、安全を確保したうえで実施します。
実際に雨漏りが発生している場所にのみ水が入ります。
事前に床養生・設備保護を徹底し、濡れてはいけない物品は完全にカバーしますのでご安心ください。
雨漏り箇所の特定に必要な最小限の水のみを使用します。
・雨天時にだけ漏水が発生する場合
・他の非破壊調査では特定が難しい場合
・複数の疑わしい部位がある場合
・図面がなく、構造が不明確な建物
など、現場での実地検証が必要な際に有効です。
再現性が高く、補修前の確実な原因特定や補修後の確認試験としても用いられます。
主にホース・ノズル・水量計・タイマー・マーキング資材などを使用します。
必要に応じて、サーモカメラや内視鏡、湿度センサーを併用し、建物内部への水の浸入を追跡します。
調査範囲の広さによって異なりますが、部分的なポイント調査であれば1〜2時間程度、
ビル全体の調査の場合は半日〜1日程度が一般的です。
建物の規模に応じて最適な調査計画をご提案します。
散水の状況・浸水が確認できた箇所・推定される原因・必要な補修内容について、
写真付きの調査報告書としてまとめてご提出します。
法人様では、長期修繕計画の資料として活用しやすいよう、図面・写真を使った分かりやすい構成にしています。
はい、調査結果を元に、最適な補修方法をご提案します。
原因箇所に合わせたピンポイント補修から、大規模修繕を見据えた計画まで対応可能です。
レインボービューシステムとは、雨漏りの原因を解明する新技術です。散水調査の際に“発光する7色の特殊液体”を流し、建物内部に浸入した水の動きを視覚的に確認できる漏水可視化システムです。
通常は見えない浸入経路が、色ごとに発光して判別できるため、複雑なルートを通る漏水でも、高い精度で原因箇所を特定できます。
ビル・マンション・工場など、大規模建物の漏水調査で特に効果を発揮します。
基本的には鉄筋コンクリート造・鉄骨造・ALC造・外壁タイルなど、ほとんどの建物で使用可能です。
特に「どこから漏れているかわからない」「複数箇所の可能性がある」建物では非常に有効です。
屋内設備・機器への影響が出ないよう、事前に使用範囲や散水量を調整します。
通常の散水調査では目視・乾燥具合・内部水跡を頼りに推測する部分があります。
一方レインボービューシステムは、浸入した水がどの経路を通って室内へ到達したのかを視覚的に確認でき、
“原因箇所だけを正確に補修できる”という大きなメリットがあります。
無駄な補修や不要な工事を避けられるため、法人様のコスト削減にも直結します。
原則として業務を止める必要はありません。
調査対象エリア周辺だけ立ち入り制限を行いますが、社内動線・来客動線に支障が出ないよう調整します。
工場や倉庫など稼働中の施設でも運用可能です。
調査前に現場確認を行い、濡らしてはいけない設備・商品・資料などは必ず養生します。
必要に応じて調査エリアを細かく分け、影響が出ないよう管理した上で作業を進めます。
調査写真・浸入経路・推定原因・必要な補修内容などをまとめた報告書形式で提出いたします。
法人様の場合、今後の大規模修繕計画に使えるよう、劣化状況の資料も併せて作成します。
調査のみのご依頼も可能です。
レインボービューシステムを用いて原因を特定したうえで、必要な補修内容をご提案いたします。
法人様の修繕計画に活用できるよう、調査結果は報告書として詳しくまとめてお渡しします。
建物規模・散水ポイント数・調査エリアの広さによって異なります。
法人様には事前見積りと調査計画書を作成し、調査の必要性と優先箇所を分かりやすくご提案します。
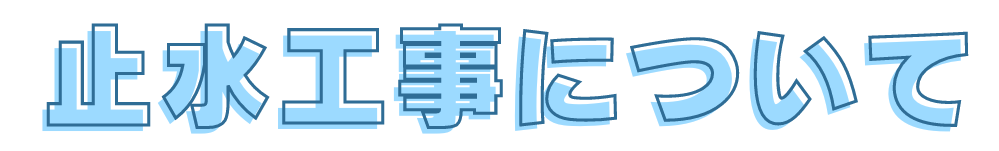
製品ジョイント部び水膨潤ゴムを張り付け製品を引き寄せて、ゴムを密着させる工法です。
ゴム自体がジョイント部の侵入水により反応して膨張することによりさらに密着します。内部・外部二重にすることも可能です。
止水工事とは、すでに発生している雨漏りを止めるための工事です。
雨水が侵入してきている箇所を特定し、補強・修復することで雨漏りを食い止めます。どちらかというと建物の内部で工事を行い、雨水の出口に線をするイメージです。(状況によっては屋外の入り口側をふさぐこともあります)
防水とは、「水が浸入することを防ぐ為に予め行う作業」のことで
止水とは、「防水機能に何らかの不具合が生じ、水が侵入してしまっている箇所を突き止め、水漏れを止める」ことです。
ここで問題なのが、雨漏りの原因は一つではないので、原因のもとを正確に調べる知識・技術が必要です。
eれべーたーが運転される空洞内のカゴが停まる際、下階床面から一番下の部分までの空間のことです。
工場の建物自体の耐久性のためにとても重要です。エレベーターピットに漏水や結露した水がたまるとエレベーター設備の老朽化を早め、ピットのコンクリートが劣化し建物の老朽化が進むので防水することが必要です。
昇降路(ピット底部を含めて)が地盤と全く接しておらず、漏水の恐れがない場合には防水処理は不要です。ただし、冷凍倉庫等にエレベーターを設置し、結露水がピットに滴下する場合には、防水処理および排水ますを設けるなどの処理が必要です。
エレベーターピットはエレベーターの地下にあります。湧水や豪雨などにより水が地下部分まで染み込み蓄積していくと、エレベーターピットの入隅部分やひび割れ部分から、ピット内に浸水することにより水が溜まってしまうことがあります。

屋根に上がれない場合、屋根の劣化が酷い場合にドローンによる調査をおすすめしております。調査時間は30分程度になります。
弊社ではどのような状況でも対応出来るように複数台の機体を所有しております。赤外線調査等にも対応しております。
可能となります。ただし、包括申請外の飛行に関しては別途国土交通省に飛行許可を申請する為に申請期間が1か月程度頂く場合がございます。私有地内での空撮に関しては問題ありません。
可能となります。(ただし別途飛行申請が必要になり条件によっては飛行不可となります。)
対応可能となります。4KやHD対応しております。その他赤外線調査も対応しております。
悪天候の場合は飛行できませんので、改めて日時を相談させていただき調査させていただきます。


お見積もり、ご相談は無料となっております。小さな事でも現場経験豊富なスタッフが対応させていただきます。
現金、お振込み、ローンなど、お客様に合った支払方法を選択していただけます。
キャンセル可能です。
クーリングオフ期間内であれば無料となります。クーリングオフ期間経過後に関してはキャンセル料が発生いたします。
基本的には工事契約内容で工事を進めていきますので追加料金等は発生いたしません。工事期間中に仕様変更や材料の変更が発生した場合には協議の上、変更いたします。
イオンクレジットサービスが利用可能です。(特別低金利実施中)
可能です。
締め日に関しては、打ち合わせ時にお伝えいただければ対応可能とな

図面がない場合でも実測を行いますので問題ありません。ただし実測の場合は調査時間を30~60分程度頂いております。
施工内容により変化致しますが、外壁最長10年、防水最長15年保証がありますのでご安心頂けます。(メーカー、施工店連盟の保証書)
弊社では施工店のみの保証は行っておりません。
工事完了後、お客様が安心して10年過ごしていただけるために施工させていただきておりますので、工事後の点検等の希望があれば無料で行っております。
施工に原因がある場合、無償での再施工対応いたします。
メーカーが基準にしている気象条件を満たさない場合は、施工中止と
天候不良による工事延期の場合は追加費用は頂いておりません。
建設一般、塗装、防水など、です。
盆栽など家の中に収納出来る物はお客様で行っていただき、
不在でも大丈夫です。
工事期間中は基本的にお部屋で乾かしていただくようになります。
工事の7日から5日前までに近隣の皆様には弊社から粗品を用意して挨拶させていただきます。工事の3日前頃からお付き合いがある住人様にはお客様自身でお声かけしていただくと、より安心して工事期間を過ごしていただけると思います。
周辺の住人様にご迷惑をおかけしないように、細心の注意をもって作業を進めておりますのでご安心ください。